アンテナ切替器 CX-310A
2011.7.11作成
目的

手持ちのアンテナ切替器 ダイアモンド(第一電波工業)のCX-310Aを引っ張り出してきました。
使用周波数はDCから800MHzまでで、リグ1台でアンテナ3本を切り替えることが可能です。中央のロータリースイッチを回すと、アンテナ1・2・3のいずれかとリグが接続されます。
高周波回路の一部なので、通過損失ばかり注目していましたが、その他の項目はどのような特性になっており、影響があるのだろうか?と気になってきました。
実用上の課題を考えながら、データを取ってみました。
機器の性能
主な規格は、裏面にシールで表示してあります。
通過損失・SWR・アイソレーションが標記されていますが、DCから500MHzまでと、500-800MHzで規格が異なっています。周波数が高いほど特性は劣化するので2段階の表示でも納得です。
入出力コネクタはM型です。一般的には430MHzまでは実用になりますが、600MHz以上になるとコネクタのインピーダンスが乱れて特性に影響が出ます。
本機器のコネクタは高周波特性を改善した形式です。中心導体−外部導体間にある絶縁物が高周波特性に影響する(線路上の誘電率が変化し、インピーダンスが乱れる)ため、以前は絶縁物の無いコネクタがありました。しかし、中心部が曲がったり折れる問題があったため、強度を維持しつつ絶縁物を最小限にとどめた本コネクタが採用されたようです。
現在のダイヤモンドブランドのモービル用ケーブルも、同じものを用いています。
中身はこれ

ボディは頑丈なアルミダイキャストですが、切替スイッチ部が気になります。裏面のネジ6本を外してみました。
入出力コネクタ間の距離が約4cmあります。スイッチの回転部はもっと短いと考えていましたが、予想外でした。このスイッチ部のインピーダンスが乱れると、SWRが大きくなり、パワーロスが増えます。
取り外したカバー(4.5mm厚)と接点間で上手くインピーダンス補正を行なっていると思われます。
接点の酸化も少なく、洗浄も不要でした。
通過損失とSWR評価
特性評価は、手持ちの測定器で可能な範囲で実施しました。
通過損失は、SG(HP8656B)とスペアナTR4131の間に本機を入れ、評価しました。
スペアナの測定分解能が0.2dBであるため、微小な損失は測定出来ませんが、明確な劣化はなく800MHzまで0.2dB以下でした。
また、SWRは手持ちの430MHzリグとSWR計+ダミーロードの間に本機を入れ評価しましたが、1.1以下で正常でした。
アイソレーション評価
アイソレーションとは、使用接点外への高周波のモレです。着目していなかった値ですが、実用に合わせて考え、データを取ってみました。従来ほど細かくデータは取らず、定性的な評価にとどめます。
アイソレーション規格は、DC-500MHzで60dB以上、500-800MHzで50dB以上です。
以下に示すグラフは、入力を0dBとした場合の出力を表示し、絶対値をアイソレーション値とします。規格はグラフに赤線で示しました。
*データはスペアナの測定限界の理由で約-73dB以下は全て同じです。決してこれ以下が
1) アンテナが接続されていない箇所へ切り替えた時のアイソレーション その1
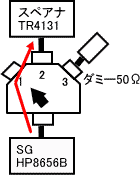
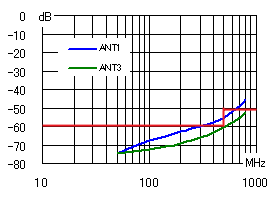
左図のようにSGとスペアナを接続します。SGをリグ・スペアナをアンテナに代用し、アンテナ1(開放)及びアンテナ3(50オーム終端)へ切り替えた際に、アンテナ2へ漏洩する出力を評価しました。
測定結果は左の通りで、アンテナ1側ではアイソレーションは300-500MHz及び650MHz以上で規格を満足しません。 430MHzでは約55dBです。
ANT3側は、ぎりぎり規格をクリアしています。アンテナ1はインピーダンス無限大でミスマッチなので、異常があって当然です。
このデータの目的は、同一周波数で極めて近い距離から電波が発射されたとき、リグの受信部を保護するためにアンテナを切り離したらどうなるか?という状況を想定したものです。
アンテナ1・3両方を開放した場合のデータも取りましたが、1と3の位置が対称であり、上記データと差が無いので省略しました。
2) アンテナが接続されていない箇所へ切り替えた時のアイソレーション その2
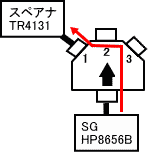
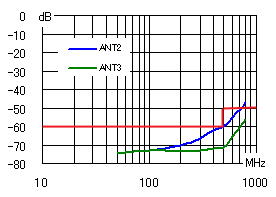
次に、アンテナ2・アンテナ3(いずれも開放)の位置を指定し、アンテナ1へ漏れる出力を調べました。
同様に結果を示しますが、隣接したアンテナ2にセットするよりはアンテナ3のほうがアイソレーション値は良好です。スイッチから距離を離せば改善されるわけです。
3) アンテナが接続されていない箇所へ切り替えた時のアイソレーション その3
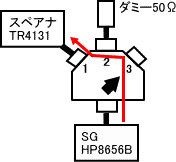
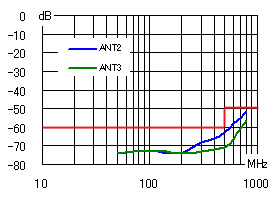
2)で、アンテナ2のみ50オームで終端しました。
アンテナ2が整合されたことで、アイソレーションは改善されています。
アンテナ3は依然として開放であり、2)と差がありません。
規格はいずれも満足しました。
4) アンテナが接続されていない箇所へ切り替えた時のアイソレーション その4
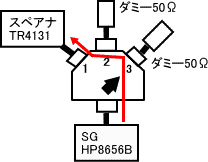
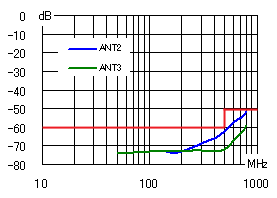
3)からさらにアンテナ3も50オームで終端しました。アンテナ3のアイソレーションが改善しました。
アンテナ3では、500MHz以下で70dB以上、500-800MHzで60dB以上になります。
以上まとめると、
1) アンテナを接続しない箇所があった場合、アイソレーションが規格を満足しないことがある
2) アンテナを接続しない箇所は、50オームのダミーを接続するとアイソレーションが改善される
3) アンテナを3本以上接続出来る場合、隣接位置よりも離れた位置のほうがアイソレーションが良い
という結論になりました。
リグ切替器としての考察
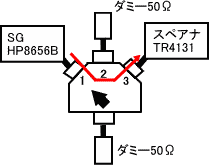
リグ切替器としての用途も気になっていました。
モノバンド・マルチバンドのアンテナに複数台のモノバンド機を接続する場合、本機を利用する方法があります。また、2台以上のリグで信号強度や音質の比較レポートをもらいたい時、切替器が使えれば便利です。
この時に気になるのが、送信したリグから送信していないリグへ加わるパワーで、これこそアイソレーションの良否にかかわります。
左のようなモデルでデータを取りました。アンテナ1に接続したリグから送信し、下側のアンテナに相当するダミーに電力を送ると、アンテナ2・3にどれだけリークするのだろうか・・・というわけです。
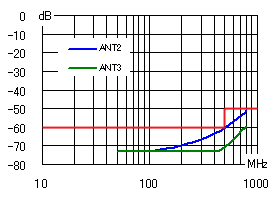
ANT3は左図のようにアンテナ2にダミーを接続して1アンテナを計測し、ANT2はダミーとスペアナの位置を入れ替えてアンテナ2を計測しました。
結果はアイソレーションその4のデータとほぼ同じでした。430MHzで70dB以上、144MHzで80dB以上は期待できそうです。
市販のデュープレクサのアイソレーションはおおむね50dB以上のようです。耐電力は十分な余裕があると思いますが、同一バンドで使用する場合は、送信しないリグの電源を切ったほうがより望ましいでしょう。
 手持ちのアンテナ切替器 ダイアモンド(第一電波工業)のCX-310Aを引っ張り出してきました。
手持ちのアンテナ切替器 ダイアモンド(第一電波工業)のCX-310Aを引っ張り出してきました。
 手持ちのアンテナ切替器 ダイアモンド(第一電波工業)のCX-310Aを引っ張り出してきました。
手持ちのアンテナ切替器 ダイアモンド(第一電波工業)のCX-310Aを引っ張り出してきました。

 ボディは頑丈なアルミダイキャストですが、切替スイッチ部が気になります。裏面のネジ6本を外してみました。
ボディは頑丈なアルミダイキャストですが、切替スイッチ部が気になります。裏面のネジ6本を外してみました。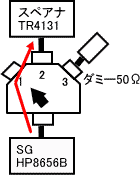
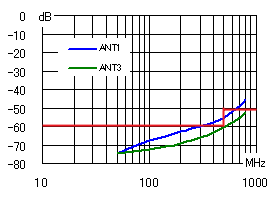 左図のようにSGとスペアナを接続します。SGをリグ・スペアナをアンテナに代用し、アンテナ1(開放)及びアンテナ3(50オーム終端)へ切り替えた際に、アンテナ2へ漏洩する出力を評価しました。
左図のようにSGとスペアナを接続します。SGをリグ・スペアナをアンテナに代用し、アンテナ1(開放)及びアンテナ3(50オーム終端)へ切り替えた際に、アンテナ2へ漏洩する出力を評価しました。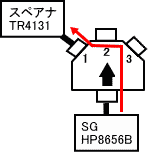
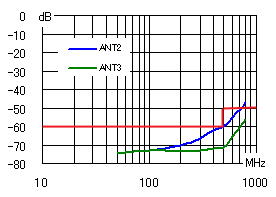 次に、アンテナ2・アンテナ3(いずれも開放)の位置を指定し、アンテナ1へ漏れる出力を調べました。
次に、アンテナ2・アンテナ3(いずれも開放)の位置を指定し、アンテナ1へ漏れる出力を調べました。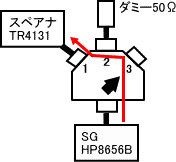
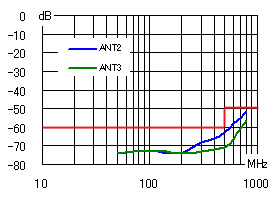 2)で、アンテナ2のみ50オームで終端しました。
2)で、アンテナ2のみ50オームで終端しました。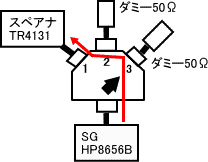
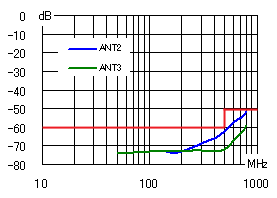 3)からさらにアンテナ3も50オームで終端しました。アンテナ3のアイソレーションが改善しました。
3)からさらにアンテナ3も50オームで終端しました。アンテナ3のアイソレーションが改善しました。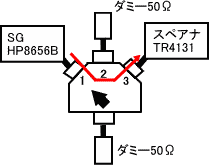 リグ切替器としての用途も気になっていました。
リグ切替器としての用途も気になっていました。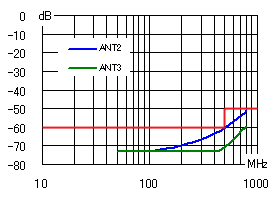 ANT3は左図のようにアンテナ2にダミーを接続して1アンテナを計測し、ANT2はダミーとスペアナの位置を入れ替えてアンテナ2を計測しました。
ANT3は左図のようにアンテナ2にダミーを接続して1アンテナを計測し、ANT2はダミーとスペアナの位置を入れ替えてアンテナ2を計測しました。