

オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。
2012.6.23作成
ヤエス FC-700
| ☆周波数 | 非公開 |
| ☆入力インピーダンス | 非公開 |
| ☆出力インピーダンス | 非公開 |
| ☆最大通過電力 | 非公開 |
| ☆挿入損失 | 非公開 |
| ☆寸法・重量 | 非公開 |
| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明
ヤエスのアンテナチューナFC-700です。トランシーバFT-707の付属品として発売されたアンテナチューナで、同じ横幅とカラーになっています。


バンドは3.5-28MHzでWARCバンドを含む8バンドで、さらにチューナを通さないスルーのポジションがあります。常時チューナを通す必要は無いので、スルー回路はあったほうが望ましいでしょう。
SWRの測定も出来ます。チューニングにSWR計は必須なので、外付けよりは内蔵のほうが便利なのは明らかです。
SWRの測定も出来ます。チューニングにSWR計は必須なので、外付けよりは内蔵のほうが便利なのは明らかです。
ダミーロードが内蔵され、150W・15Wのパワーも計測出来るので(精度は別として)終端型パワー計として使えます。
但し、ダミーはリレーで切り替えるので、リレーをドライブする電源DC8Vが必要です。FT-707からDC8Vが取り出せるようですが、取説ではDC13Vが使えるように改造方法が記載されています。
但し、ダミーはリレーで切り替えるので、リレーをドライブする電源DC8Vが必要です。FT-707からDC8Vが取り出せるようですが、取説ではDC13Vが使えるように改造方法が記載されています。
内部の解析
 上部カバーを開けると、バリコン・コイルが目にとまります。最大通過電力150Wなので、妥当なデバイスです。
上部カバーを開けると、バリコン・コイルが目にとまります。最大通過電力150Wなので、妥当なデバイスです。バリコンとロータリースイッチは、全てタイトカップリングでツマミとつながれます。小さいバリコン(290pF)はロータがGNDに落ちていますが、チューナ自体のGNDが不安定な場合、カップリングが無いとツマミに触れただけで同調が不安定になる可能性があります。コストアップになりますが、安定した動作が期待出来ます。
写真奥にある抵抗は50オームダミーで、5W1Kオームの抵抗を20本並列接続しています。HF帯なので、周波数特性の補正は不要でしょう。
ダミーの位置の上下カバーは、放熱の長穴が開いています。取説には、連続キャリアは30秒以内にする旨の注意書きがあります。
ダミーの位置の上下カバーは、放熱の長穴が開いています。取説には、連続キャリアは30秒以内にする旨の注意書きがあります。
 インピーダンス50オームに近いアンテナを用いる場合、ダミーロードでおおよそのマッチングを取ってからアンテナに切り替えれば、チューニングが楽です。
インピーダンス50オームに近いアンテナを用いる場合、ダミーロードでおおよそのマッチングを取ってからアンテナに切り替えれば、チューニングが楽です。 コイルは21/24/28MHzがメッキ線の空心コイルだけで動作し、18MHz以下はさらにトロイダルコアに巻いたコイルが直列接続されます。
特性評価
同調を取った後にSGとスペアナで周波数特性を調べた結果を下記に示します。
各バンド別データを重ね、各レンジの関係を明確にしました。見やすくするため、WARCバンドの3バンドは別グラフにしました。
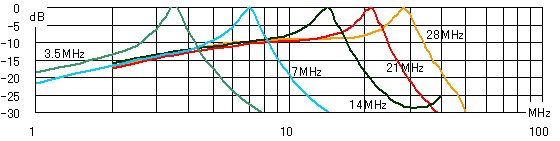
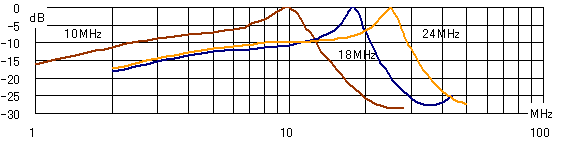
低い周波数は減衰量が少なく、高い周波数で多いローパスに近い特性です。
各バンドの特性をさらに以下に表現しました。
各バンド別データを重ね、各レンジの関係を明確にしました。見やすくするため、WARCバンドの3バンドは別グラフにしました。
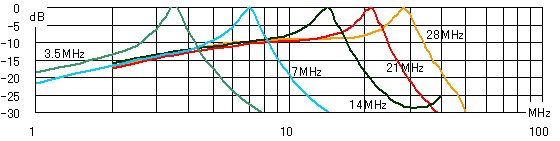
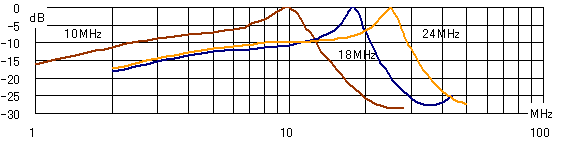
低い周波数は減衰量が少なく、高い周波数で多いローパスに近い特性です。
各バンドの特性をさらに以下に表現しました。
| 3.5MHz | 7MHz | 10MHz |
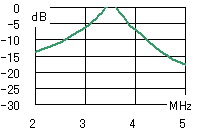 |
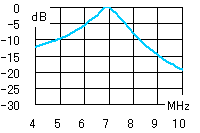 |
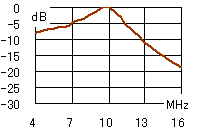 |
| 14MHz | 18MHz | 21MHz |
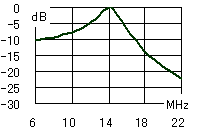 |
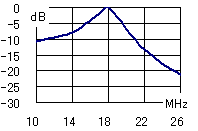 |
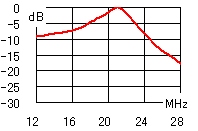 |
| 24MHz | 28MHz |
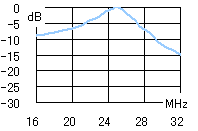 |
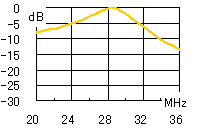 |
調整
パワー表示のボリューム調整と、反射波表示の調整だけです。
パワーは従来のパワー計調整の方法で確認、無調整でOKでした。
反射波表示は100Wの電力を入れ、反射波の表示が最小になるようにトリマを回すだけです。
パワーは従来のパワー計調整の方法で確認、無調整でOKでした。
反射波表示は100Wの電力を入れ、反射波の表示が最小になるようにトリマを回すだけです。
その他
アンテナチューナのデータをいくつか取りましたが、Qが高からず低からず適当なようです。通過帯域が狭いと不要輻射には有利ですが、チューニングがクリチカルになり、バンド内の上下で再調整が必要になります。
コンテストのような同時運用の時に、相互の干渉をどこまで改善出来るか試してみたいと考えています。
コンテストのような同時運用の時に、相互の干渉をどこまで改善出来るか試してみたいと考えています。