
富士測定器の終端型パワーメータです。ジャンク一式で入手したものの中にありました。 「富士測定器」は、スイッチで有名な「フジソク」の前身です。
かなり古い製品で、製造年月日が1962年(昭和37年)8月です。周波数は54-68Mcと表記されていますが、防災無線等の業務で使われた周波数のようです。メータは1971年製に交換されています。
ダミーロードを内蔵しています。ケース周辺に通風穴が多数あり、シールドの点で不安はありますが、この時代なら許されていたのかもしれません。
大きな特徴は、熱電対を用いた計測であることです。熱電対型電力計は電子工学の書籍でしか知りませんでしたが、今回初めて手にすることになりました。
電力で発生する熱を熱電対で検出し、発生した電流でメータを振らせます。電流が流れ、発熱するまでに時間的な遅れがあるので、直接メータを振らせる方式に比べ、応答速度は良くありません。

メータパネルの熱電対を表すマーク、ご存じでしょうか。左写真の矢印の箇所です。
フジソクは現在も終端型電力計を製造していますが、『出力波形歪みによる測定誤差がない』という点を強調しています。この方式は、プロ用計測器として生きていたんですね。

後と側面のネジを外すと、リアパネルとダミーロードが取り出せます。ダミーロードは1Kオームの抵抗を20本並列接続しています。
円柱状に抵抗が並んでおり、数を数えたら17本しかありません。上下のハンダ付け箇所から、内部に3本入っていることがわかりました。高周波インピーダンス補正のノウハウかもしれません。
ダミーロードは、リアパネルのM型コネクタにハンダ付けされたネジで固定しますが、この間にパワーの検出部がありました。分解した状態が左下写真です。
現物に関して知識がなく、webで検索しても有用な情報が出てきませんでした。

さて、原理をご存じの方はお教え下さい・・・と書いて本ページを公開した晩、手元の書籍*で原理を発見しました。
画像で上記に掲載します。
*JARLアマチュア無線ハンドブック
JARLアマチュア無線連盟 1968年発行
検出部は左写真のもので、トロイダルコアの外周に導線が巻かれており、そばにあるガラス管が熱電対です。大変シンプルな構造ですが、これで測定できるとは驚きです。
トロイダルコアで高周波電流を検出することは、市販の通過型パワー計でもおなじみですが、この電流を直流メータを振らせるための整流ダイオードが問題で、特性バラツキで測定精度が低下します。
熱電対型は電気エネルギーを熱エネルギーに変換して測定しますが、熱電対はばらつきが少なく安定しています。
50MHzで使えそうなので、パワー(連続キャリア)を入れてみましたが、メータの針がゆっくりと振れます。発熱して電流が流れるまでのタイムラグがあり、SSB向きではありません。
12Wのパワーを入力しましたが、ほぼ同じ表示を示します。メータの調整ボリュームはなく、メータそばの巻線(電流調整の抵抗)をいじるようですが、特に作業は不要でした。
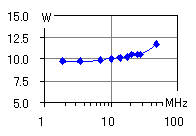
ダミーでHFから50MHzまで十分使えますが、パワー計として他のバンドで使えないだろうか・・・と測定値を調べてみたのが、左図です。
入力パワーPi=12W F=1.9-50MHzで測定
28MHz以下は50MHzに比べ1-2.5Wの誤差が出ます。他バンドの活用は難しそうですが、見方を変えれば
メータの振れを調整すればHF帯のパワー計として使えます。14MHzで合わせ込めば、1.9-28MHzで±5%の精度です。
こんな活用方法もあります。
アマチュアのパワー計では見かけない構造です。電子計測の教科書も、原理は書いてあっても実物は出ていません。
SSBやCWのような連続でない電波の場合、実効電力が表示されるのでしょうか。不思議な計測器を見てしまった感覚がありますHi。
古い計器なので、ネジは全て旧JISネジです。劣化したM3ネジはISOネジに交換、ネジ込みました。
 富士測定器の終端型パワーメータです。ジャンク一式で入手したものの中にありました。 「富士測定器」は、スイッチで有名な「フジソク」の前身です。
富士測定器の終端型パワーメータです。ジャンク一式で入手したものの中にありました。 「富士測定器」は、スイッチで有名な「フジソク」の前身です。

 富士測定器の終端型パワーメータです。ジャンク一式で入手したものの中にありました。 「富士測定器」は、スイッチで有名な「フジソク」の前身です。
富士測定器の終端型パワーメータです。ジャンク一式で入手したものの中にありました。 「富士測定器」は、スイッチで有名な「フジソク」の前身です。 メータパネルの熱電対を表すマーク、ご存じでしょうか。左写真の矢印の箇所です。
メータパネルの熱電対を表すマーク、ご存じでしょうか。左写真の矢印の箇所です。 後と側面のネジを外すと、リアパネルとダミーロードが取り出せます。ダミーロードは1Kオームの抵抗を20本並列接続しています。
後と側面のネジを外すと、リアパネルとダミーロードが取り出せます。ダミーロードは1Kオームの抵抗を20本並列接続しています。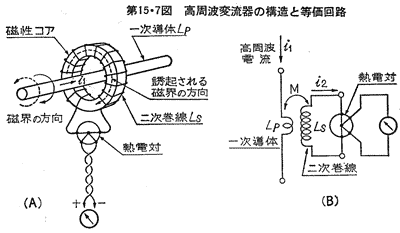
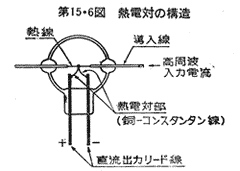
 さて、原理をご存じの方はお教え下さい・・・と書いて本ページを公開した晩、手元の書籍*で原理を発見しました。
さて、原理をご存じの方はお教え下さい・・・と書いて本ページを公開した晩、手元の書籍*で原理を発見しました。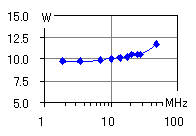 ダミーでHFから50MHzまで十分使えますが、パワー計として他のバンドで使えないだろうか・・・と測定値を調べてみたのが、左図です。
ダミーでHFから50MHzまで十分使えますが、パワー計として他のバンドで使えないだろうか・・・と測定値を調べてみたのが、左図です。