 違反の事例を こちら に掲載しています。
2004.6.22作成
|
| ☆周波数・モード | 144MHz、430MHz FM |
| ☆定格出力 | 非公開 |
| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |
| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |
| ☆受信方式 | 非公開 |
| ☆受信感度 | 非公開 |
| ☆通過帯域幅 | 非公開 |
| ☆電源 | 非公開 |
| ☆消費電力 | 非公開 |
| ☆寸法・重量 | 非公開 |
| ☆発売年・定価 | 非公開 |
2010.9.26
オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。
オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。
このリグの説明
144/430MHzの2バンドを1台で運用出来る初のモービル機として発売されました。ただし、同時受信はまだ先の話で、中間周波増幅部以降を共通に構成しています。
大型の液晶表示が採用された点でも、当時は画期的だったと思います。
大型の液晶表示が採用された点でも、当時は画期的だったと思います。
オークションで入手しました。「中古リグ6台まとめて\8,250」の中にあった1台、完全動作を期待していませんでした(笑)。
PLL回路
発振出力は十分ですし、ロックが外れる現象もありません。周波数のみ調整しました。
送信周波数を確認すると、144MHzで+300Hz、430MHzで+1.3KHzでした。周波数調整のトリマTC4を動かし、誤差100Hz程度に収めました。
送信周波数を確認すると、144MHzで+300Hz、430MHzで+1.3KHzでした。周波数調整のトリマTC4を動かし、誤差100Hz程度に収めました。
受信部
 受信は出来ました! 感度も悪くなさそうですが、ボリュームにガリがあります。聞こえなくなったり、ガリガリという音がしてノイズが聞こえてきたりで安定しません。
受信は出来ました! 感度も悪くなさそうですが、ボリュームにガリがあります。聞こえなくなったり、ガリガリという音がしてノイズが聞こえてきたりで安定しません。右写真のように分解し、ボリュームの隙間に接点復活剤を少し吹き付けました。ほんの少し穴に吹きかけ、少し待ってから繰り返し回転させます。2回繰り返しましたが、決して大量に流し込んではいけません。これで接触は正常になりました。その後1週間以上経過しても、問題はありません。
まず144MHzの受信感度を測定します。信号を入力し、それぞれSのバーグラフが点灯し始めるレベルを測定しました。バンド内で2dBμのばらつきがあります。
145.20MHzの信号を入力し、バーグラフが多く点灯するように初段のRF(高周波)コイル・IF(中間周波数)のコイル等を調整しました。微妙なところは難しいので、バーグラフを表示するための信号出力部にテスターを当て、最大になるようにしました。
さらに、いつものようにバンドパスフィルタ(ヘリカルキャビティ)の調整です。3箇所の調整が必要ですが、145.20MHzで最大感度になるように真ん中のネジを回し、次に144.70MHzでRF増幅側のネジ、145.80MHzでIF増幅側のネジを回して最大感度にします。この3つの作業を数回繰り返します。
帯域はアマチュアバンドのFMの運用範囲に絞られますが、この範囲の感度は上昇します。
145.20MHzの信号を入力し、バーグラフが多く点灯するように初段のRF(高周波)コイル・IF(中間周波数)のコイル等を調整しました。微妙なところは難しいので、バーグラフを表示するための信号出力部にテスターを当て、最大になるようにしました。
さらに、いつものようにバンドパスフィルタ(ヘリカルキャビティ)の調整です。3箇所の調整が必要ですが、145.20MHzで最大感度になるように真ん中のネジを回し、次に144.70MHzでRF増幅側のネジ、145.80MHzでIF増幅側のネジを回して最大感度にします。この3つの作業を数回繰り返します。
帯域はアマチュアバンドのFMの運用範囲に絞られますが、この範囲の感度は上昇します。
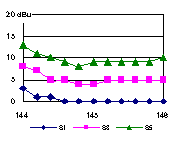
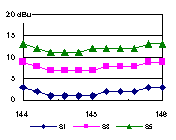 調整前後のバンドの感度を測定した結果が左のグラフです。横軸が周波数、縦軸が入力信号レベルです。
調整前後のバンドの感度を測定した結果が左のグラフです。横軸が周波数、縦軸が入力信号レベルです。表現上わかりにくいとは思いますが、どのように書いたらよいのか考えずにデータを取ってしまったものですから、ご勘弁を。
分かりやすく言えば、Sで1つ上昇したことになります。
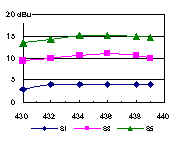
 同様に430MHzも受信感度を測定します。ここも2dBuのばらつきがあります。431.00MHzと438.00MHzで2個のキャビティを調整しました。バランスを取るように繰り返し行いましたが、一方の感度を上げるともう一方が犠牲になってしまいます。
同様に430MHzも受信感度を測定します。ここも2dBuのばらつきがあります。431.00MHzと438.00MHzで2個のキャビティを調整しました。バランスを取るように繰り返し行いましたが、一方の感度を上げるともう一方が犠牲になってしまいます。通常のQSOを主体にするので、低い周波数で感度を良くすることにしました。
431〜434MHzでSが0.5程度上昇しました。
 さらに、433.0MHz 20dBuの信号でSのバーグラフが全灯するように調整しました。
さらに、433.0MHz 20dBuの信号でSのバーグラフが全灯するように調整しました。このリグは共通の中間周波増幅部から信号を検出しており、バンド別に調整は出来ません。430MHzは144MHzに比べてSで1つ表示が少なくなっています。
但しS表示の直線性は良く、おおよそ3dBuでS1つになります。
送信部
144MHzは最初11.0W出ましたが、ドライブ段のトリマを調整すると11.5Wになりました。ファイナルはモジュールですからほとんど調整不要ですが、パワー調整の可変抵抗がついているのがクセモノです。
パワーモジュールの場合、多くは出力を制御する回路が内蔵されています。モジュールに加える制御電圧で出力を変化出来るのです。この可変抵抗を回しきると、最大13.5Wまで出るようになりました。
パワーモジュールの場合、多くは出力を制御する回路が内蔵されています。モジュールに加える制御電圧で出力を変化出来るのです。この可変抵抗を回しきると、最大13.5Wまで出るようになりました。
430MHzは11.0W出ましたが、440MHzで10.0Wと少し出力が低下しました。144MHzと同様にドライブ段のトリマとキャビティを調整し、バンド内でほぼ均一の出力を得ました。さらに、パワーモジュール制御の可変抵抗を回すと14.5Wになりました。
送信周波数は±1KHz以下に収まっており、問題なしです。
その他
さすがジャンク扱いされたリグ、外観も内部も汚れていました。
まず内部です。プリント基板がベタついた感じに見えます。ハンダのフラックスが付着したかのようです。綿棒にアルコールを付けて基板を拭きました。綿棒の先はすぐに茶色になりました。細かなところはあきらめましたが、少し安心しました。

次にコイルです。右の中央のコイル(キャビティ)が洗浄後、その左右にある2個のキャビティが洗浄前です。結構きれいでしょ!?
炭酸水素ナトリウムを少しの水で練ったような状態にし、ボロ切れと綿棒につけて拭きました。その後、残った粉をアルコールで拭きました。最終的には送信部分も含め4個のキャビティを磨きました。
炭酸水素ナトリウムを少しの水で練ったような状態にし、ボロ切れと綿棒につけて拭きました。その後、残った粉をアルコールで拭きました。最終的には送信部分も含め4個のキャビティを磨きました。
「炭酸水素ナトリウム」・・・どんな薬品?とお思いでしょうか。実は「重曹」です。薬屋さんで簡単に買えます。銀メッキの酸化したものをきれいにするには効果絶大です。但し、アルミを腐食させるので、ご注意を。また、水を入れすぎると基板へ流れてしまい、除去できなくなります。

フロントパネルもひどいものでした。液晶と液晶保護の透明アクリルパネルの内側に汚れがありました。分解し(写真の通り)、汚れを中性洗剤を染み込ませたティッシュペーパーで拭きました。
ツマミやスイッチも洗剤をつけたボロ切れで拭きました。
ちょっと失敗したのは、フロントパネルの側面をアルコールで拭いたら色落ちしたことです。樹脂(ABSでしょうか)に銀色の塗装をしていたんですね。
ツマミやスイッチも洗剤をつけたボロ切れで拭きました。
ちょっと失敗したのは、フロントパネルの側面をアルコールで拭いたら色落ちしたことです。樹脂(ABSでしょうか)に銀色の塗装をしていたんですね。
あとは両横のプラスチック部品です。ここにモービルブラケットがつきますが、表面が茶色に変質しています。
物理的な変質ですから、洗浄しても効き目がありません。耐水ペーパーで磨き、地のグレーに近い色を出しました。
 右が元の状態、左が磨いたものです。完全にきれいになる前に表面が削られて平らな板になりそうだった(Hi)ので、適当なところでやめました。
右が元の状態、左が磨いたものです。完全にきれいになる前に表面が削られて平らな板になりそうだった(Hi)ので、適当なところでやめました。
物理的な変質ですから、洗浄しても効き目がありません。耐水ペーパーで磨き、地のグレーに近い色を出しました。
 右が元の状態、左が磨いたものです。完全にきれいになる前に表面が削られて平らな板になりそうだった(Hi)ので、適当なところでやめました。
右が元の状態、左が磨いたものです。完全にきれいになる前に表面が削られて平らな板になりそうだった(Hi)ので、適当なところでやめました。 それにしても、随分汚れていたものです。
前オーナーはどんな環境にこのリグを置いていたのでしょうか?
前オーナーはどんな環境にこのリグを置いていたのでしょうか?
