 従来の144MHzFM機は水晶発振方式でしたが、このリグはトリオとして初めてPLLで多チャンネル化を実現しました。50チャンネル切り替え可能なロータリースイッチと2ケタの7セグメントLEDによる周波数表示が特徴です。2ケタの表示は100KHz・10KHz単位の数値を表示します。
従来の144MHzFM機は水晶発振方式でしたが、このリグはトリオとして初めてPLLで多チャンネル化を実現しました。50チャンネル切り替え可能なロータリースイッチと2ケタの7セグメントLEDによる周波数表示が特徴です。2ケタの表示は100KHz・10KHz単位の数値を表示します。
オークションの無断リンクがあるので、仕様は非公開です。
2006.9.9作成
2007.10.1修正
2009.2.20修正
2010.9.26追記
2007.10.1修正
2009.2.20修正
2010.9.26追記
トリオ TR-7500
| ☆周波数・モード | 非公開 |
| ☆定格出力 | 非公開 |
| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |
| ☆FM最大周波数偏移 | 非公開 |
| ☆受信方式 | 非公開 |
| ☆受信感度 | 非公開 |
| ☆通過帯域幅 | 非公開 |
| ☆電源 | 非公開 |
| ☆消費電力 | 非公開 |
| ☆寸法・重量 | 非公開 |
| ☆発売年・定価 | 非公開 |

リグの説明
 従来の144MHzFM機は水晶発振方式でしたが、このリグはトリオとして初めてPLLで多チャンネル化を実現しました。50チャンネル切り替え可能なロータリースイッチと2ケタの7セグメントLEDによる周波数表示が特徴です。2ケタの表示は100KHz・10KHz単位の数値を表示します。
従来の144MHzFM機は水晶発振方式でしたが、このリグはトリオとして初めてPLLで多チャンネル化を実現しました。50チャンネル切り替え可能なロータリースイッチと2ケタの7セグメントLEDによる周波数表示が特徴です。2ケタの表示は100KHz・10KHz単位の数値を表示します。本機では1回転50チャンネルのロータリースイッチが採用され、20KHzステップでちょうど1MHzをカバーすることで非常に便利になりました。これ以前のリグはPLL機であってもチャンネル切り替えのスイッチが12もしくは24接点でしたし、ダイオードマトリックスで周波数設定をせねばなりませんでした(ユニデン2010、アイコムIC-250が、これに該当します)。
後継機種のTR-7500GRとともに、ベストセラーでした。
後継機種のTR-7500GRとともに、ベストセラーでした。
使用できる周波数は、オリジナルでは145MHz台(145.00-145.98MHz)だけです。
1978年1月1日よりJARL推奨の使用区分が変更になり、144.32-145MHz未満がFMで使用出来なくなりました。同時にFM帯域幅も40KHz以下から20KHz以下になりました。区分変更発表後に発売されたリグですから、144MHz台は不要(というよりも、違反する局を増やさないためでしょう)なのと、ロータリースイッチでは50チャンネルの1MHz可変が精一杯だという事情もあったようです。まだロータリエンコーダではないのです。
144MHz台はオプションの水晶1個をスイッチで切り替えます(AUXスイッチ)。入手したリグにも入っており、144.00-145.98MHzまで送受信可能です。水晶を交換すれば146・147MHz台も受信可能です。
1978年1月1日よりJARL推奨の使用区分が変更になり、144.32-145MHz未満がFMで使用出来なくなりました。同時にFM帯域幅も40KHz以下から20KHz以下になりました。区分変更発表後に発売されたリグですから、144MHz台は不要(というよりも、違反する局を増やさないためでしょう)なのと、ロータリースイッチでは50チャンネルの1MHz可変が精一杯だという事情もあったようです。まだロータリエンコーダではないのです。
144MHz台はオプションの水晶1個をスイッチで切り替えます(AUXスイッチ)。入手したリグにも入っており、144.00-145.98MHzまで送受信可能です。水晶を交換すれば146・147MHz台も受信可能です。
オプション水晶が実装されていない場合、PLLがアンロックになるのでULIのLEDが点灯します。
 |
 |
| 上面図 | 下面図 |
受信部
 まず最初に気づいたのが、オプション水晶装着済の144MHzが受信出来ないことでした。もちろん送信もできません。
まず最初に気づいたのが、オプション水晶装着済の144MHzが受信出来ないことでした。もちろん送信もできません。PLLがロックしていないので、水晶の不良か?と思いましたが、水晶はOKでした。144MHz台の信号をSGで入力しVCOのトリマ(右写真)を少し回したところ、突然受信できるようになりました。VCOへの印加電圧がずれていたようです。
動作確認すると、144MHz台のロックが遅く1秒くらいかかっていました。VCO電圧を144.00MHzで約3.0V程度まで上げたところ、問題なくロックするようになりました。
信号を入力すると、十分使用できるレベルにあるようですが、メーター(このリグはS表示がありません)の振れが辛めに感じます。初期特性を取り、各種コイルを調整しました。下図のように目盛り2つ程度振れが大きくなりました。
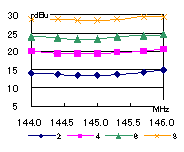 |
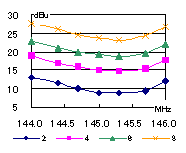 |
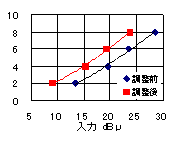 |
| 調整前 | 調整後 | S特性(F=145.00MHz) |
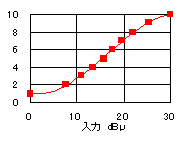 (2009.2.20修正)
(2009.2.20修正)受信の中間周波増幅以降で2SC460を8本使用しています。スケルチが閉じにくい問題があったので、全て2SC829に交換しました。受信感度も向上し、スケルチも問題なく閉じるようになりました。
受信感度は、1uV入力でS/N32dBでした(F=145.00MHz)。
メータは30dBuでフルスケールになるように調整しました。最終の特性は右の通りです。
送信部
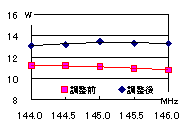 送信出力は約11W出ていましたが、調整すると約13Wになりました。ドライブTr 2SC1169の入力回路トリマTC1調整で効果がありました。
送信出力は約11W出ていましたが、調整すると約13Wになりました。ドライブTr 2SC1169の入力回路トリマTC1調整で効果がありました。送信周波数は700Hz程度のズレです。10.7MHzの水晶発振回路に変調をかけるのですが、この周波数が500Hz程度低かったので、調整しました。
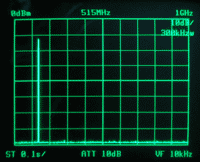 (2009.2.20修正)
(2009.2.20修正)スプリアス特性を修正しました。2次高調波は-70dBに近く、良好です。
F=145.00MHz、 X:100MHz/div、 Y:10dB/div
変調も確認、マイクゲイン・デビエーションとも現状のままでOKでした。
その他
PLL回路がしっかり説明書に公開されています。以降のTR7500GRから、PLL回路のみ一般に非公開になりました。受信改造はもちろんですが、知識のある人なら送信改造も可能だからでしょう。