 違反の事例を こちら に掲載しています。
2005.4.7作成
|
| ☆周波数・モード | 144MHz FM |
| ☆定格出力 | 非公開 |
| ☆最大周波数偏移 | 非公開 |
| ☆送信周波数構成 | 非公開 |
| ☆受信周波数構成 | 非公開 |
| ☆マイクインピーダンス | 非公開 |
| ☆受信方式 | 非公開 |
| ☆受信感度 | 非公開 |
| ☆通過帯域幅 | 非公開 |
| ☆電源 | 非公開 |
| ☆消費電力 | 非公開 |
| ☆寸法・重量 | 非公開 |
| ☆発売年・定価 | 非公開 |
2010.9.26
オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。
オークションの無断リンクが依然としてあるので、上記仕様を非公開とします。
このリグの説明
 144MHzのモービル機として人気があったTR-7200シリーズの第三作目です。前作のTR-7200G発売中にFMのナロー(狭帯域)化が進められたため、本機は帯域40KHzのワイドFMと20KHzのナローFMをスイッチで切り替えるように設計されています。
144MHzのモービル機として人気があったTR-7200シリーズの第三作目です。前作のTR-7200G発売中にFMのナロー(狭帯域)化が進められたため、本機は帯域40KHzのワイドFMと20KHzのナローFMをスイッチで切り替えるように設計されています。ナロー化に伴い、周波数ズレがある信号を受信すると了解度が低下しますので、補正するRITツマミが登場しました。RITの可変幅は±4.5KHz以上だそうです。
また、ツマミを引くとSメータがセンターメータとして動作します。FM機としては珍しいでしょう。
 ジャンク扱いで2台を入手しました。1台はケースの塗装が傷だらけで送信パワーが少なく、もう1台はツマミが無く受信感度が良くありません。2台を組み合わせて「ニコイチ」にします。前者をベースにし、後者から部品を取ることにします。ケースを入れ替え、水晶も前者に無い周波数を追加します。
ジャンク扱いで2台を入手しました。1台はケースの塗装が傷だらけで送信パワーが少なく、もう1台はツマミが無く受信感度が良くありません。2台を組み合わせて「ニコイチ」にします。前者をベースにし、後者から部品を取ることにします。ケースを入れ替え、水晶も前者に無い周波数を追加します。受信部
 受信感度はあまり悪くなさそうです。いつもの方法で各コイルを調整し、受信感度を改善しました。初期データが無くなってしまったので、データは省略します。
受信感度はあまり悪くなさそうです。いつもの方法で各コイルを調整し、受信感度を改善しました。初期データが無くなってしまったので、データは省略します。 第二発振回路の水晶の横にあるコイルでRITの周波数を調整します。SGで4KHz変調の信号を加え、RITツマミを回して周波数を上下させてバランスを取りながら最適点を探しました。±10KHzくらい変化するようですが、ナローフィルタの特性上±5KHzが使用範囲です。もっとも、今のリグは3KHz以上もズレて送信することなどあり得ませんHi。
左に2つ縦に並んでいるのが受信用セラミックフィルタです。左がナロー、右がワイドですが、もはやワイドは不要ですね。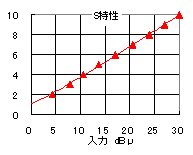
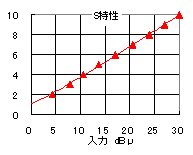
S表示は30dBuでフルスケールになるようにしました。TR-7200、7200Gに比べると直線性があります。
受信感度は1uV入力でS/N29dBと、スペックを少し割るようですが、十分使用可能でしょう。
尚、このリグは後ろに受信感度の切り替え(DX-LOCAL)スイッチがあります。これを見落としてLOCALのまま10W送信すると、「耳が悪い」と言われますので注意が必要です。
受信感度は1uV入力でS/N29dBと、スペックを少し割るようですが、十分使用可能でしょう。
尚、このリグは後ろに受信感度の切り替え(DX-LOCAL)スイッチがあります。これを見落としてLOCALのまま10W送信すると、「耳が悪い」と言われますので注意が必要です。
送信部
最初は出力がわずか6Wでした。いくら調整しても変化ありません。一方、部品取り機は12Wも出ます。
フタを開けると、部品取り機はトランジスタが2SC1956から2SC2102に交換してありました。規格を調べると、ほぼ同等です。
取り外し交換してみましたが、変化ありません。トランジスタが原因では無さそうですので、元に戻しました。
フタを開けると、部品取り機はトランジスタが2SC1956から2SC2102に交換してありました。規格を調べると、ほぼ同等です。
取り外し交換してみましたが、変化ありません。トランジスタが原因では無さそうですので、元に戻しました。
 2台を並べてドライブ段からのレベルを自作の高周波プローブで調べて比較します。ファイナル入力で差があることがわかりました。ドライブ部のトリマ・コンデンサを新品に交換しても変化ありません。不思議に思い各部品をじっくりと眺めたら・・・・・何と!ドライブ出力コイルがハンダで1回分ショートしています。(右の丸の箇所)
2台を並べてドライブ段からのレベルを自作の高周波プローブで調べて比較します。ファイナル入力で差があることがわかりました。ドライブ部のトリマ・コンデンサを新品に交換しても変化ありません。不思議に思い各部品をじっくりと眺めたら・・・・・何と!ドライブ出力コイルがハンダで1回分ショートしています。(右の丸の箇所)タップ出力をハンダ付けした時に誤ってハンダブリッジさせたのでしょう。メーカー出荷時か修理時の問題でしょうか?? ハンダを除去し、再調整すると8W出るようになりました。でも、まだ不十分です。ファイナル入力回路のレベルがまだ低いようです。
ファイナル2SC1956のベース−GND間のコンデンサ47pFを65pFのトリマに交換してみると10W出るようになりました。さらに固定コンデンサを追加すると、約90pFで最良点が見出せました。
しかし、従来の2倍の容量でマッチングが取れるのは変です。その他周辺部品を交換しても状況は変わらないので、諦めて部品取り機のモジュールと丸ごと交換することにしました。
さて、交換するとパワーが13W出ます。真の原因が知りたいところですが仕方ない・・・・・と思っていたら、連続送信しているうちに徐々にパワーが低下して5Wくらいになる現象が発生しました。一旦受信に戻し、すぐに送信すると再び13Wを示します。トランジスタや部品の発熱とは考えられません。
回路図が無いので、手持ちのTR-7200Gの回路図(PDFで解像度が悪く、困っていますがHi)で代用して考えました。 ** その後、コピーを入手しました。
回路図が無いので、手持ちのTR-7200Gの回路図(PDFで解像度が悪く、困っていますがHi)で代用して考えました。 ** その後、コピーを入手しました。
ファイナル部の電圧をテスターで調べると、同様に低下していきます。しかも最初でも11.5V程度しか印加されていません。この電圧はリレーを介して電源から供給されています。リレーまでたどって電圧を測定すると、何とリレー通過後の電圧が降下していきます!送信の最初でもリレー接点間で1V近くドロップします。
 早速リレーを外して接点洗浄剤でクリーニング、再び取り付けるとパワーが徐々に下がる現象は無くなりました。接点の汚れが問題だったようです。ところが、まだ接点間の電圧降下が約0.5Vあります。今後の安定性を考え、部品取り機のリレーを外して接点洗浄し、交換しました。今度はパワーが14W、接点間の電圧降下も0.1V程度と問題なくなりました。
早速リレーを外して接点洗浄剤でクリーニング、再び取り付けるとパワーが徐々に下がる現象は無くなりました。接点の汚れが問題だったようです。ところが、まだ接点間の電圧降下が約0.5Vあります。今後の安定性を考え、部品取り機のリレーを外して接点洗浄し、交換しました。今度はパワーが14W、接点間の電圧降下も0.1V程度と問題なくなりました。リレーはソケットに差し込んであり、直接ハンダ付けではありません。保守の点では助かります(消耗品だから当然かな?)。左写真のケース上に乗っているのが、今回不具合のあったリレー、その左下の3本の白線がハンダ付けされている黒い部品がリレーソケットです。
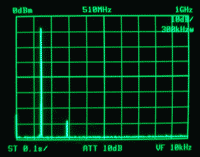 以上の対策後に全回路を調整し、水晶の実装されている144.72〜145.60MHzで14.5W出るようになりました。
以上の対策後に全回路を調整し、水晶の実装されている144.72〜145.60MHzで14.5W出るようになりました。変調部はオーバーデビエーション気味でしたので、変調度計で確認しながら調整しました。マイクゲインは、マイク感度との整合性がありますので、別のトランシーバでモニターしながら調整しました。
(2007.3.25追記)スプリアス特性を取りました。2倍高調波が-60dB、何とかクリアしています。
その他
水晶発振子を用いたトランシーバを調整すると、水晶の劣化が多いのに驚かされます。実数を数えていませんが、1割はありそうです。(TR-7200G」と製品名まで記載されていて純正部品相当であっても、です。)
発振しない「劣化」もありますが、ここで問題なのは発振周波数が数十KHzもズレてしまう場合です。周波数補正のトリマで補正しきれないのです。周波数が低くなるものばかりですが、20KHz低下するとちょうど隣のチャンネルに使えてしまいますHi。まあ、安定性がどのくらいあるかが問題ですが・・・・。
発振しない「劣化」もありますが、ここで問題なのは発振周波数が数十KHzもズレてしまう場合です。周波数補正のトリマで補正しきれないのです。周波数が低くなるものばかりですが、20KHz低下するとちょうど隣のチャンネルに使えてしまいますHi。まあ、安定性がどのくらいあるかが問題ですが・・・・。
前述のワイド/ナローFM切り替えスイッチですが、現在はワイドで送信すると隣接周波数に妨害を与えます。いずれスイッチの配線を変更し、ワイドを無効にする予定です。操作を誤っても大丈夫な「フール・プルーフ」は大切です。
同様に、受信のDX-LOCALの切り替えもDXのみとしましょう。
同様に、受信のDX-LOCALの切り替えもDXのみとしましょう。
