
IC-38と同一デザインの144MHzFM機です。IC-27に比べ奥行が小さくなり、大きな液晶表示になりました。大きな液晶表示は1985年にIC-2300で採用されてから各社で広まったようです。
IC-37では小さなプッシュボタンが13個も並び、操作性に難がありました。本機ではボタンを9箇所にし、大きくしたので使いやすくなりました。
なぜボタンが大きくなったか?と言えば、マイクコネクタがフロントパネルから消えたからです。裏から出ているケーブルにマイクを接続しますが、延長ケーブルが必要な場合もあります。IC-38をご参照下さい。
 |
 |
| 上面図 |
下面図 |
入手したリグは受信改造されていたので、元に戻しました。抵抗1本の変更だけですが、詳細は書きません(書けません)Hi。
スケルチのボリュームが劣化しており、通常の位置(9時-10時)でノイズが消えません。ボリュームを少し引っ張るとノイズが止まります。テスターでチェックしましたが、内部の摺動部が浮き上がって接触不良を起こしているようです。メーカーから部品を入手して交換しましたが、アイコムの小型ボリューム(A社製)は同様の不具合が多数確認されます。
高周波増幅部は出力同調回路にバリキャップを用いて帯域を可変しています(マルの箇所)。PLL制御ICのデジタル出力を周波数とともに変化するアナログ電圧に変換し、バリキャップに加えています。通過帯域を狭めて感度向上と隣接周波数の影響を防ぐ効果がありますが、アマチュア無線以外の隣接周波数の受信性能を高める狙いもあるように思えます。
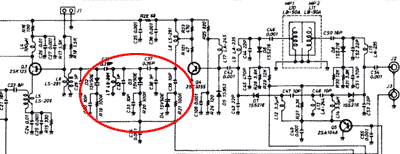

受信感度は悪くないようですが、アマチュアバンドに絞って調整しました。下記のグラフのようにS2つくらい改善されました。周波数に対しフラットな特性なのは、上記の同調回路だからでしょう。
高周波増幅の入力コイル(ヘリカルと思われます)は横に取り付けられており、通常の調整ドライバが入りません。高さの制約で設計されたのでしょうが、これは考えものです。結局、調整は止めました。
なお、出力コイル間に見える黄色の部品がバリキャップです。
感度は標記方法が異なりますが、1uV入力でS/N35dBでした。十分な性能を維持していると思います。
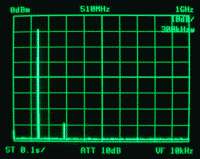
送信回路、出力に関しては実は何も触れる箇所がありません。ハイパワー・ローパワーの調整しか無いのです。
バンド幅2MHzの範囲で10.5-11.0W出ており、通常レベルでした。
変調もチェックしましたが、全く調整不要でした。
前後しますが、周波数のズレも100Hz以下、これまた手をつけませんでした。
PLLで直接144MHzを発振させ、変調ををかけています。ミキサーもないので、近接スプリアスの心配もなさそうです。
一応2倍高調波はギリギリながらクリアしています。
X: 100MHz/div、 Y: 10dB/div、 F=145.00MHz
受信部の高周波増幅部の出力同調回路ですが、バリキャップの印加電圧を数MHz毎に切り替える程度の回路と考えていました。設定ボリュームがあるかな?と見ても、それらしきものはなく、チャージポンプ回路でアナログ電圧に変換していました。
手の込んだ構成ですが、140-160MHzあたりまでの広帯域受信を狙ったものかもしれない・・・・と再度考えた次第です。
 IC-38と同一デザインの144MHzFM機です。IC-27に比べ奥行が小さくなり、大きな液晶表示になりました。大きな液晶表示は1985年にIC-2300で採用されてから各社で広まったようです。
IC-38と同一デザインの144MHzFM機です。IC-27に比べ奥行が小さくなり、大きな液晶表示になりました。大きな液晶表示は1985年にIC-2300で採用されてから各社で広まったようです。

 IC-38と同一デザインの144MHzFM機です。IC-27に比べ奥行が小さくなり、大きな液晶表示になりました。大きな液晶表示は1985年にIC-2300で採用されてから各社で広まったようです。
IC-38と同一デザインの144MHzFM機です。IC-27に比べ奥行が小さくなり、大きな液晶表示になりました。大きな液晶表示は1985年にIC-2300で採用されてから各社で広まったようです。

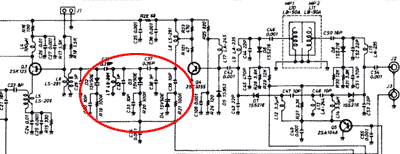
 受信感度は悪くないようですが、アマチュアバンドに絞って調整しました。下記のグラフのようにS2つくらい改善されました。周波数に対しフラットな特性なのは、上記の同調回路だからでしょう。
受信感度は悪くないようですが、アマチュアバンドに絞って調整しました。下記のグラフのようにS2つくらい改善されました。周波数に対しフラットな特性なのは、上記の同調回路だからでしょう。
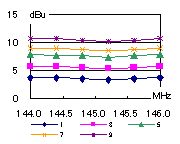
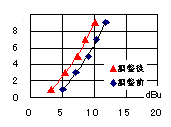
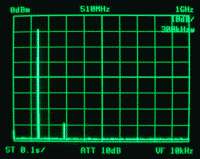 送信回路、出力に関しては実は何も触れる箇所がありません。ハイパワー・ローパワーの調整しか無いのです。
送信回路、出力に関しては実は何も触れる箇所がありません。ハイパワー・ローパワーの調整しか無いのです。